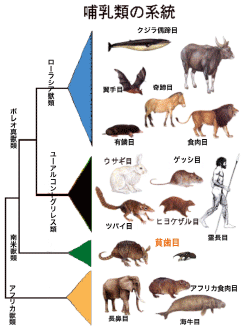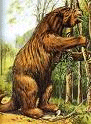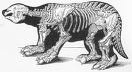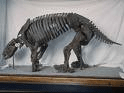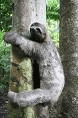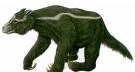学名
界 Animalia 動物界
門 Chordata 脊椎動物
綱 Mannalia 哺乳綱
目 Xenarthra 貧歯目(異節目)
科 Myrmecophagidae アリクイ科
属 Myrmecophaga オオアリクイ属
種 Myrmecophaga tridactyla オオアリクイ
アリを食べるために進化してきたオオアリクイの形態
真獣類(現生の哺乳類のうち単孔類、有袋類以外のもの)の目レベルはボレオ真獣類(北半球のローラシア大陸起源)、アフリカ獣類(アフリカ起源)、南米獣類(貧歯類)(南アメリカ起源)の3つの主要なグループに分類でき、大陸の分裂、移動と密接に関わっていることが分かる。このうちオオアリクイは南米獣類に分類される。
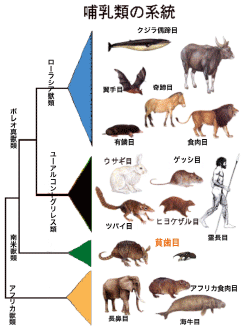
貧歯類(Edentate)とは元来「歯のない」という意味であるが、古くは食性の著しい特殊化に伴って歯がひどく単純化したり、退化したり、あるいは消失している哺乳類に対して人によっていろいろに使われていた。しかし現代的な意味では、この言葉は南アメリカ大陸で進化し新世界の外へは広がらなかった哺乳類の特定の目だけを指すのに用いられる。
貧歯類で最も古いのは古欠歯類(亜目)と呼ばれるもので、北アメリカの第三世紀前期の堆積物から出ている。これらの化石動物は後世の貧歯類の直接の祖先であったわけではないが、おそらくこの目のうちの根源的な祖先形と類縁が遠くない原始的なメンバーの遺物なのだろうとみられている。古欠歯類のなかで保存状態の最も良いのは、始新世のMetacheiromys(図1)で、大きさも体の比率も今のアルマジロぐらいの小さい動物だった。四肢は短めで、足には鋭い鉤爪があり、尾は太くて長い。頭骨は丈が低く、前後に長い。特に重要なのは歯牙がひどく変形していたことである。切歯と頬歯はほとんど全く消失しているが、犬歯はわりあい大形で、鋭く劣った木の葉状の歯として残っていた。その他の古欠歯類のなかには、頬歯が残ってはいるがエナメル質がほとんどなく、ただのクイ状のものに退化してしまっている種類があった。歯の生えかわりが無い貧歯類の歯は、乳歯系または永久歯系のどちらかが、一方的に発達して、他の系が消失したものといわれる。このグループの動物は北アメリカでは斬新世の末まで生存していたが、この地域の第三世紀前期の動物相のなかでもさほど数多くいたわけではなかったようである。
 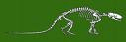
図1 Metacheiromys
そうするうちに初期の貧歯類は南アメリカへも侵入していき、第三紀前期まであった両アメリカ大陸のつながりが切れる前にこの大陸に根をおろすようになった。それ以来貧歯類は南米大陸の中にあって、外海から全く隔離された状態で進化してきた。やがてかれらは休息に南アメリカの動物相の重要な成員になりあがり、そのまま今に至っている。
ところで、貧歯類に起こったいくつかの特色の発達は、これらの動物をひどく局限された生活様式へ早くから特色化させることになり、祖先の食虫類から受け継いだ原始的な特徴を覆い隠してしまった。背中の各腰椎の間には付加的な異節型(xenarthrous)の関節が発達して、脊柱のこの部分を著しく補強するようになった。またある種類では、頸椎の数が哺乳類のほとんどすべてに共通の7個より多く、9個に増えている。足には大きな鉤爪が発達している。脳は比較的小さく原始的だったが、これは現在の貧歯類でも同じである。頬骨弓は一般的に不完全で、1本につながっていない。また、歯はひどく退化して単純な形になるか消失してしまった。
第三世紀に入ると、より高等な貧歯類が二つの大きな適応放散の系統にそって発展する。その一つは被甲類という亜目で鎧をそなえたアルマジロやグリプトドンの類が属し、もう一つが地上性ナマケモノ(絶滅)、樹上性ナマケモノ、そしてアリクイを含む系統である。このグループは有毛類という一つの亜目とされている。
新生代後期に入ってから、有毛類は体の巨大化という大きな進化をとげる。また、皮膚の中に丸石を敷き詰めたように多数の骨片が埋まっているのも大きな特徴であった。骨格がどこも頑丈にできており、脚には非常に太い骨があった。足はいずれも大きく、土を掘るのに使ったらしい鉤爪がついている。現存する同類と同じように、後ろ足ではその外側縁を、前足では握るように曲げた時に突き出る指の関節を地について歩行したことが明らかである。頭骨は前後にいくらか長く、歯はやはり顎骨の両脇にだけあって、いずれもクイ状を呈していた。Megatherium(図2)のような最大級のものになると小型のゾウくらいの大きさで、重さもトン単位である。また、かれらは草木の葉を主食物とする植食性の動物だったと見られる。
さらに進化を遂げるとアリクイの類はMyrmecophaga(図3)という地上性の貧歯類になる。これがオオアリクイである。吻部が管のように長く突き出しているので頭骨は前後に大変長い(図4)。この吻はアリ塚やシロアリの巣に探りを入れるのに使われるが、それとともに非常に長くのばすことのできる舌と粘々した唾液があり、これで常食物のアリをなめ取るのである。歯は全く消失している。鉤爪は恐ろしく大きくて鋭く尖っていて、アリやシロアリのすみ家を掘るのに使われるだけでなく、強力な武器にもなる。歩く時は祖先と変わらず後ろ足ではその外側縁を、前足では握るように曲げた時に突き出る指の関節を地について歩行する。
図4頭蓋骨
鮮新世後期になると、南北両アメリカ大陸が第三世紀前期のように一度地峡で繋がった結果、さまざまな動物が北から南へ侵入してきた。長期間、外の世界から孤立した島や大陸における生物は生存競争に弱い傾向がある。侵入してきた動物はたくさんの南米土着の哺乳類を絶滅させたが、貧歯類だけはこれを免れた。貧歯類の中には北方からの打撃に持ちこたえただけではなく逆に北方へ広がったものもいたが、オオアリクイは北へは広がらなかった。
まーとーめー
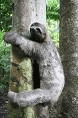 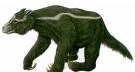 
樹上生ナマケモノ ← 地上性ナマケモノ → オオアリクイ
|